
月刊『We learn』2001年9月号(No.587)
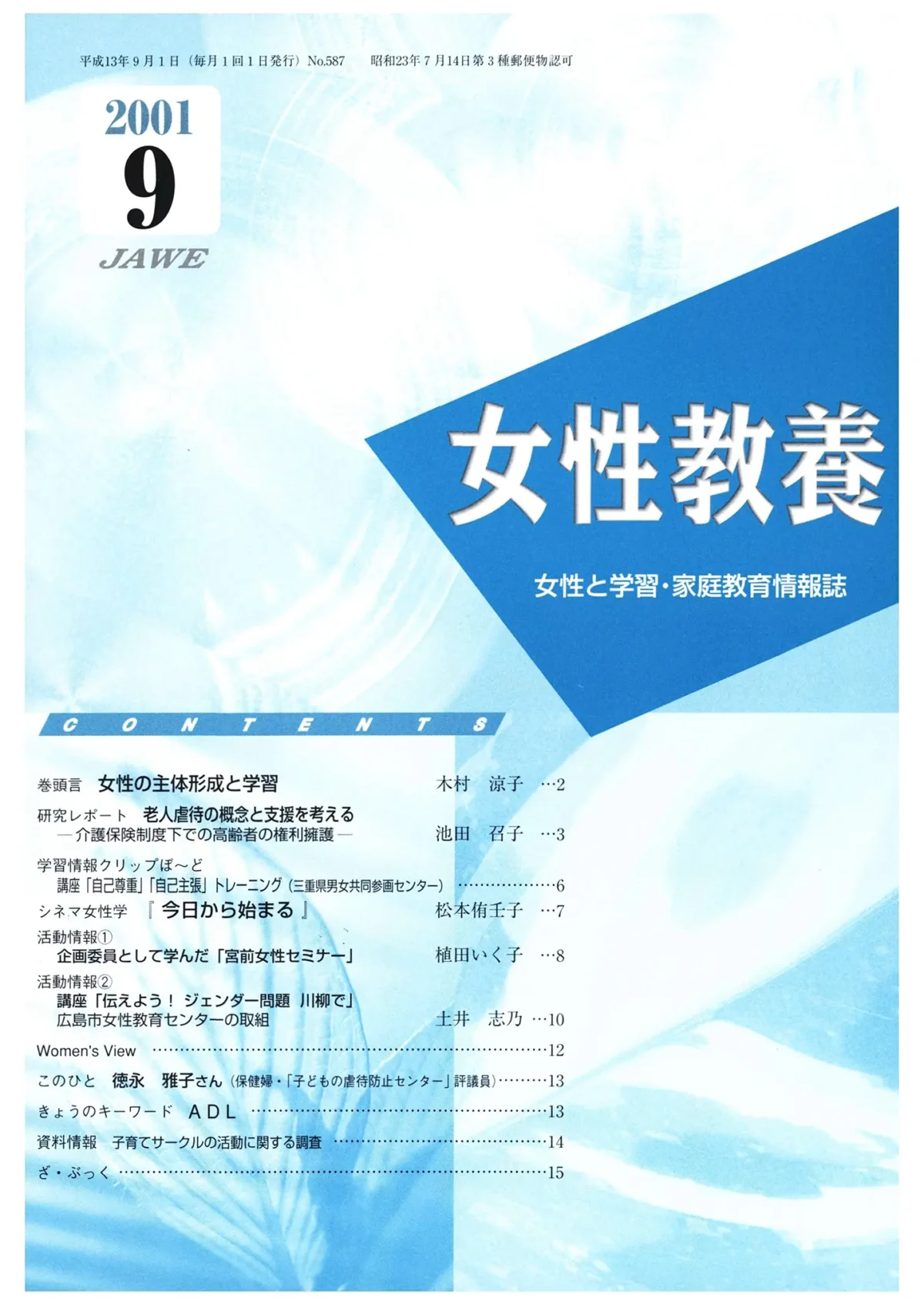
特集:
研究レポート
老人虐待の概念と支援を考える/池田召子
介護保険制度下での高齢者の権利擁護
学習情報クリップぼ~ど
「自己主張」「自己尊重」トレーニング(三重県男女共同参画センター)
シネマ女性学
『今日から始まる』
フランス映画/ティファニー・タヴェルニエ監督
教育は生きている/松本侑壬子
活動情報(1)
企画委員として学んだ「宮前女性セミナー」/植田いく子
活動情報(2)
講座「伝えよう!ジェンダー問題川柳で」/土井志乃
広島市女性教育センター
Women’s View
参画に必要な条件とは/合田美津子
「力の解放」としてのエンパワーメント/横尾ちえ
このひと
徳永雅子さん(保健婦・「子どもの虐待防止センター」評議員)
きょうのキーワード
ADL
資料情報
子育てサークルの活動に関する調査/子育てサークル研究会(国立女性教育会館内)
巻頭言
女性の主体形成と学習
木村涼子(きむらりょうこ)
学びながら自分が変わっていくことは、楽しい。
そういう実感をもって、多くの女性がさまざまな場で学んでいる。80年代から90年代にかけて性差別が社会問題として認識されるとともに、学習活動によって自分自身が抱える課題と向き合っていこうとする女性がふえていることのあらわれといえよう。そうした学習活動は、「自分探し」の旅でもある。
女性問題が学習課題として取り上げられる場面では、女性学習者の主体形成の視点が欠かせない。そこで目指されるのは、女性に対する差別や抑圧を認識し、女性のおかれた状況を自ら変革していく主体である。性差別に立ち向かうということには、自分の外部にある抑圧との闘いと、自分の中に内面化されている抑圧との闘いという、2つの面がある。固定的な性役割意識や女らしさ・男らしさの特性観、男性優位の考え方などは、日常生活のすみずみに浸透し、女性自身にも内面化されている。「自分は女だからだめだ」「女は男に従うもの」「女の幸せはやはり男性につくすこと」といった考え方や気持ちが、女性から自信や自由を奪っている。
女性が「学ぶ」ということは、新しい知識や技能を習得するだけでなく、自分自身を見つめ、内なる抑圧から自らを解放していくプロセスでもあるべきだろう。ボーヴォワールは「女は『女』につくられる」と書いたが、社会的・文化的に「つくられる」柔軟性をもった私たちは、「女」としてつくられた自分を「つくりかえる」力をもった存在でもある。
学びながら自分が変わっていくことは、楽しい。一直線の「進歩」でなくていい。右往左往しながら、変わっていきたい。
プロフィール
大阪女子大学教員。大学生時代に佐藤洋子著『女の子はつくられる』(白石書店)と出会い、自分が女性であること、受験競争の中で育ってきたことを見つめなおすために、教育社会学を専攻。以来、性別の社会化と教育、男女平等と教育を研究テーマとしている。著書『学校文化とジェンダー』(勁草書房)、『教育の社会学』(共著、有斐閣)、『女の文化』(共著、岩波書店)など。
※PDFの印刷、配布、無断転載等はご遠慮ください。
