
月刊『We learn』2004年3月号(No.617)
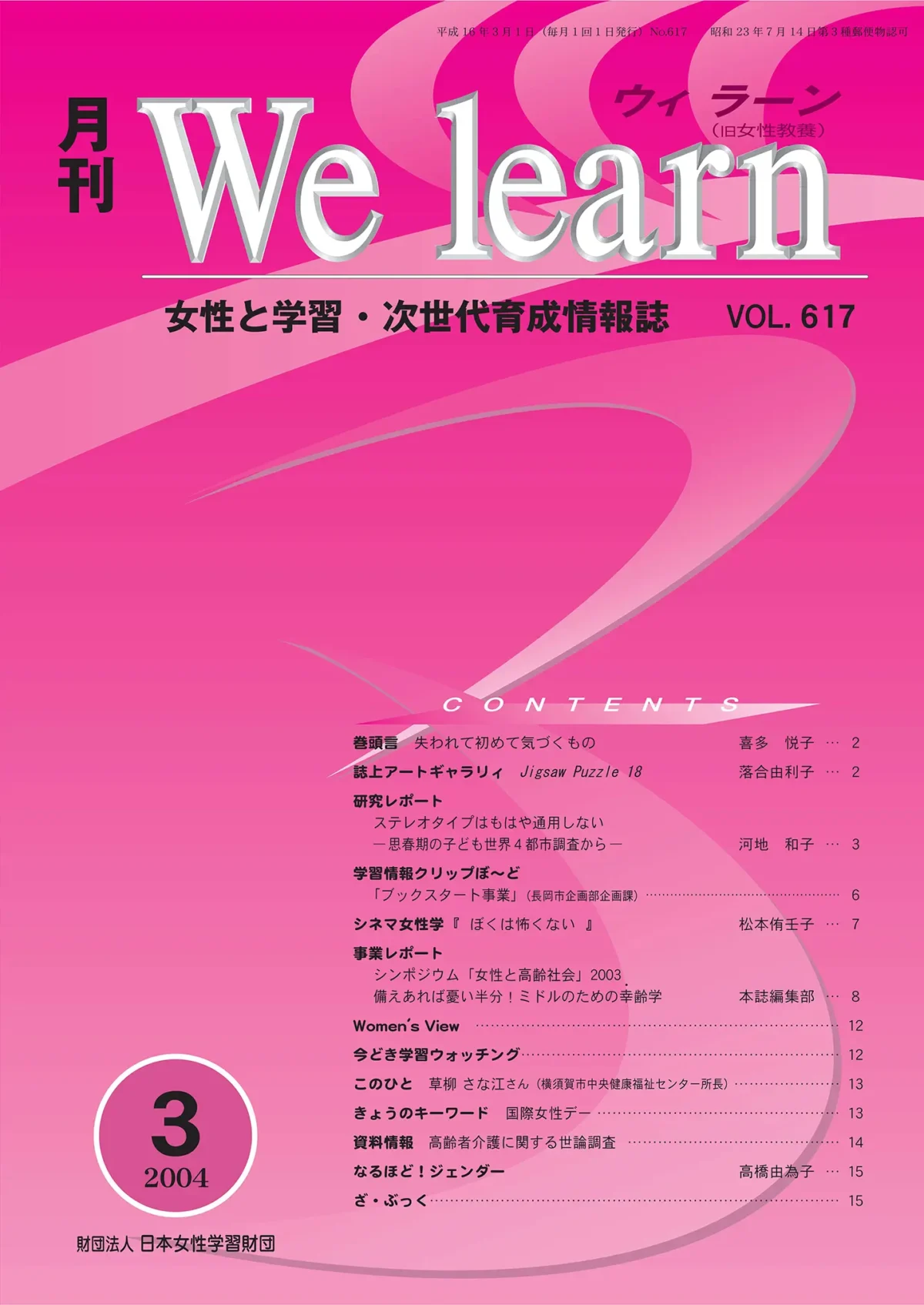
特集:
誌上アートギャラリィ
フォトエッセイJigsaw Puzzle18/落合由利子
研究レポート
ステレオタイプはもはや通用しない-思春期の子ども世界4都市調査から-/河地和子
学習情報クリップぼ~ど
ブックスタ-ト事業/長岡市企画部企画課
シネマ女性学
『TAIZO』『ぼくは怖くない』
イタリア映画(109分)/ガブリエ-レ・サルヴァト-レス監督
あえて愛する父に背いて/松本侑壬子
事業レポ-ト
シンポジウム「女性と高齢社会」2003
備えあれば憂い半分!ミドルのための幸齢学/本誌編集部
Women’s View
シンポジウムがくれた気づき/島田宏子
高齢社会を生きる-シンポジウム「女性と高齢社会」に参加して/岩澤まりも
今どき学習ウォッチング
ファシリテ-タ-考
このひと
草柳さな江さん(横須賀市中央健康福祉センタ-所長)
きょうのキーワード
国際女性デ-
資料情報
高齢者介護に関する世論調査(内閣府)
なるほど!ジェンダー
政治は女の出る幕じゃない?/イラスト:高橋由為子
巻頭言
失われて初めて気づくもの
喜多悦子(きたえつこ)
人は、誰しも健康でいたいと願っているはずだ。
だが、アッチが痛い、コッチが痛いとか、老眼になった…などという、あえて言えばミクロの健康問題は口にしても、個々人が、もてる能力を適正に発揮し、社会や地域の活力となるだけでなく、自分を含む地域や国のwell-beingの保持向上に必須の、マクロ観点の健康については、あまり考えていないようにみえる。多分、ほどほどの生活をしていて、こんなものだと満足しているか、あるいは、それを考えるゆとりのない生き方を余儀なくされているか、だろう。マクロの観点でみた健康の、本当に重要な意義は、個々人の生き方だけでなく、その個人が属する家族、一族、地域社会そして国の発展にかかわっているのだが、それに気づくことはめったにない。
開発途上国の保健医療サービスの改善にかかわる機会をもって、まもなく20年になる。この間、貧しいだけではなく、さまざまな紛争が続いている国や地域を数多くみる機会があったが、健康と平和と地域社会のidentity(こころの拠り所)は、それが失われて初めて、いかに重要なものであったかに気づくことを実感する。失われて初めて気づくようなものは、簡単に復活できない、と私は考える。だから、それを失わないために大いなる努力が必要なのだ。
紛争地や貧しい国では、人は生まれながらに平等ではない、と思う。生まれる場所も時代も選べないにもかかわらず、たった1年の、いや1週間1時間の健康の保障もないところに、生まれてくる赤ん坊の何と多いことか。ある国、ある地域が平和で、独裁などではなく、適正な治安が維持され、防ぎうる病気で多数の子どもや大人が命を失わずにすむところは、オンナもオトコも、すべての人々が等しくマクロ的に健康であるはずだ。
プロフィール
兵庫県宝塚市生まれ。医学博士。日本赤十字九州国際看護大学教授。早稲田大学大学院客員教授。小児科・血液学の臨床・研究・教育後、国際保健分野に転身。ODAプロジェクト(国立国際医療センター)、難民援助(UNICEFアフガニスタン事務所)、アフリカ、バルカン、中央アジアの紛争地の保健支援(WHO本部)などでの実践経験が豊富。2003年にエイボン女性大賞、2004年には国際ソロプチミスト千嘉代子大賞を受賞。
いまどき学習ウォッチング
ファシリテーター考
先日あるワークショップで、ファシリテーターとは何かを体験する時間があった。まず2人1組となる。一人が部屋を出て自由に歩き、もう片方はファシリテーター役となって相手に付き添う、というものだ。あまり話さないように、という指示が講師からあった。
前と後ろ、あるいは横に並んで、ペアでそれぞれが施設内を数分間歩く。役割を交替し、体験後はグループで感想を述べ合った。自由に歩く側は「見守られているとはこんな感じなのかな」「一緒にいられると、ちょっとけむったいような気も」「困ったらSOSが言えそう」。ファシリテーター役からは「どう声かけすればよいか迷った」「相手との距離のとり方が難しい」など、体験ら湧き出た意見が次々とあがる。
今、参加型学習にファシリテーターは欠かせないが、その技術を学ぶ機会はそう多くない。技術の前に、相手の気持も自分の気持も尊重し合い、それに必要な距離感を体得することが大事だということが、おぼろげながらわかってきた。学習者と学習支援者の双方でつくりあげる関係、相手の自由を保障するための役割―ファシリテーターは奥が深い。
※PDFの印刷、配布、無断転載等はご遠慮ください。
